動画編集の基礎中の基礎とも言えるのが「カット編集」です。
どれだけ凝った演出をしても、カットがグダグダだと動画全体の印象が悪くなります。
この記事では、私自身が副業として動画編集を始めてから
実際の案件の中で身につけてきた「カット編集のリアルなテクニック」をご紹介します。
初心者がつまずきやすいポイントや
細かいけど仕上がりに大きく差が出るコツを具体的にまとめました。
🔰これから動画編集を始めようと思っている方は、まず最初に
【未経験→副業】30代会社員が動画編集を始めたきっかけと理由 を読んでいただくのがおすすめです。
波形を見れば、無駄な部分が見えてくる…でも音もちゃんと聞こう
私がカット作業で一番意識しているのは「波形を見ること」です。
音声の波形が動いていない部分は、基本的に無言の時間。そこはためらわずにカットしています。
また、言い淀みや「あー」「えー」といったつなぎ言葉も
波形を見ると谷になっていることが多いので
その部分でカットすれば編集によるノイズも最小限に抑えられます。
ただし、波形だけに頼りすぎるのは危険です。
たとえば、「さしすせそ」のように息を抜くような発音や
「たちつてと」のような破裂音で始まる言葉は
波形上では無音やノイズと見分けがつきにくいことがあります。
波形はあくまで“目安”として使い、必ず実際の音も聴いて判断することが大切です。
編集は視覚と聴覚の両方を使って、ベストなタイミングを見つける作業だと思っています。
前後の話の流れを見て判断する
カットの判断で迷うのは、話が前後でつながっている場面や会話がかぶった場面です。
特にインタビュー編集では、複数人が同時に話し始めることもあり
どちらの音声を活かすべきか迷うケースもあります。
そのときは、前後の流れを確認したうえで
視聴者にとって意味が通じやすい方を優先して残すか
クライアント様のご意向を確認するようにしています。
大事なのは「何を削るか」ではなく「何を伝えたいか」を基準に判断することです。
無音をとにかく細かく切る
視聴者の集中力を保つために、私は無音の間を細かく切るようにしています。
話の間が長すぎるとテンポが悪くなり、離脱の原因にもなります。
特に間延びしてしまう部分や、ショート動画等でテンポ感が大切な場合は
Premiere Proの「速度デュレーション」を使って125%くらいに再生速度を上げて調整します。
ただし、速度を変更すると音声が高くなってしまうため
「ピッチシフター」というオーディオエフェクトを使って補正をかけています。
私が125%の速度デュレーションの時に使用する設定はこちらです
- セミトーン:-3
- セント:-86
- 精度:高精度
- 「適切なデフォルト設定を使用する」にチェック
速度を変えた際の音程補正の数値は、log2(再生速度)^12 で理論的に計算できますが
私は Google で「ピッチシフター 計算」などと検索して調整しています。
カット編集は“細かさ”が差を生む
カット編集は、地味で時間がかかる作業ですが
ここを丁寧にやることで動画のクオリティが大きく変わります。
特にインタビューやビジネス系の動画では
視聴者にとって「テンポよく見られる」ことが何より重要です。
- 波形を見る
- 無音を切る
- テンポを意識する
この3つを意識するだけでも、初心者から一歩抜け出した編集ができるようになります。
まとめ
- 波形を見て無言部分を的確にカット
- 前後の文脈を意識して判断
- 無音は切る、間延びは速度変更で調整
- ピッチ補正で違和感をなくす
- 波形だけでなく、音もしっかり聴いて判断する
カット編集は、特別なセンスがなくても確実に上達できる作業です。
最初はうまくいかなくても、「どうしたらもっと見やすくなるかな?」と試行錯誤を繰り返す中で
編集に自分らしさができてきます。
迷っている方も、ぜひ自分のペースでカット編集の感覚をつかんでみてください。

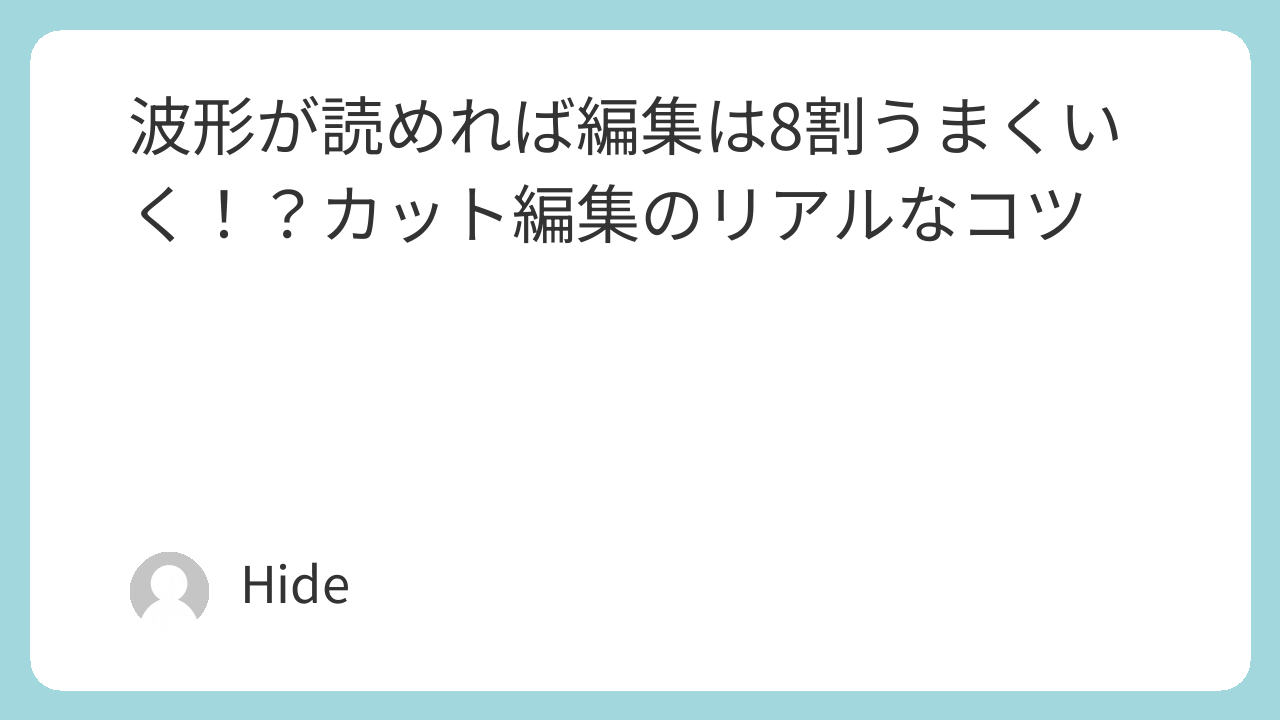
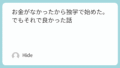
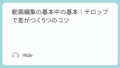
コメント